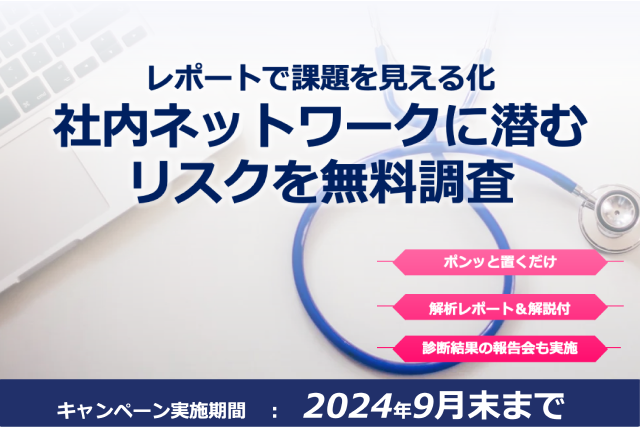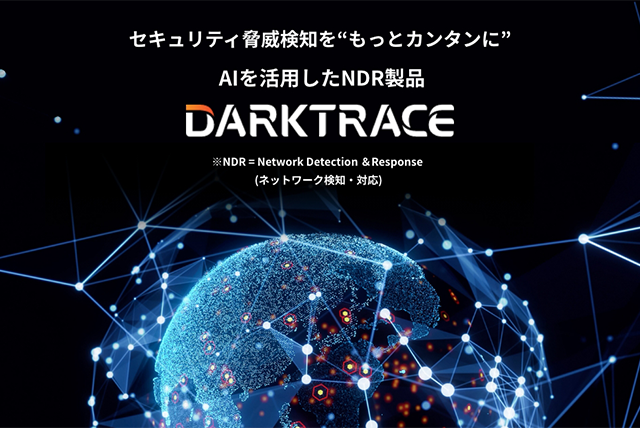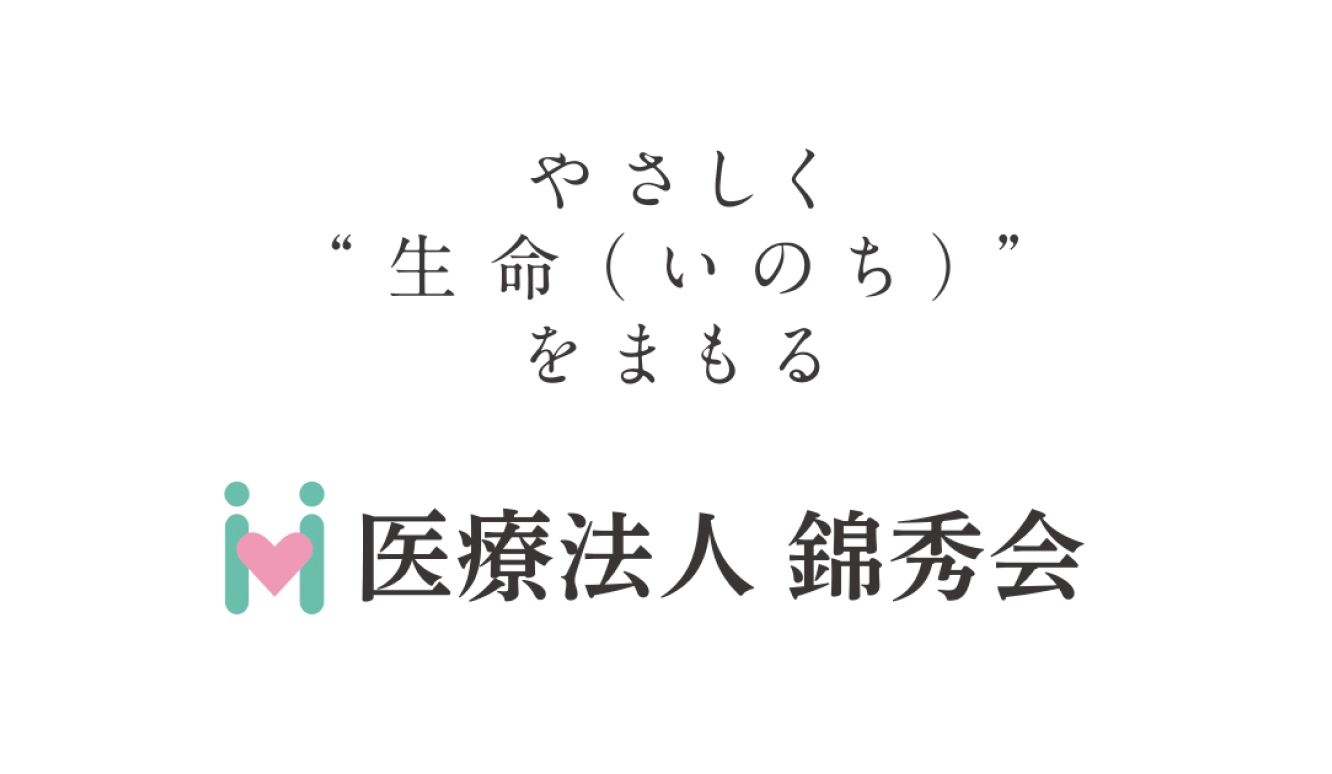さまざまな業界の企業にご利用いただいています
プロフェッショナル
サービスとは
巧妙化するサイバー攻撃や、新たに発見される脆弱性・情報漏洩事故など、企業が抱えるセキュリティリスクは増大しています。
「LANSCOPE プロフェッショナルサービス」は、最新の攻撃手法と最適な対応策を探求するセキュリティプロフェッショナルチームがサービスを提供しています。
※「SecureOWL(セキュアオウル)」は「LANSCOPE プロフェッショナルサービス」にブランド変更しました。
脆弱性も、攻撃の兆候も見逃さない
今必要なセキュリティ対策をご提供
セミナー
お役立ち資料
-

LANSCOPE プロフェッショナルサービス
脆弱性診断サービスのご紹介 -

3分でわかるNDR製品「ダークトレース」
-

クラウドセキュリティ診断
サービスのご紹介